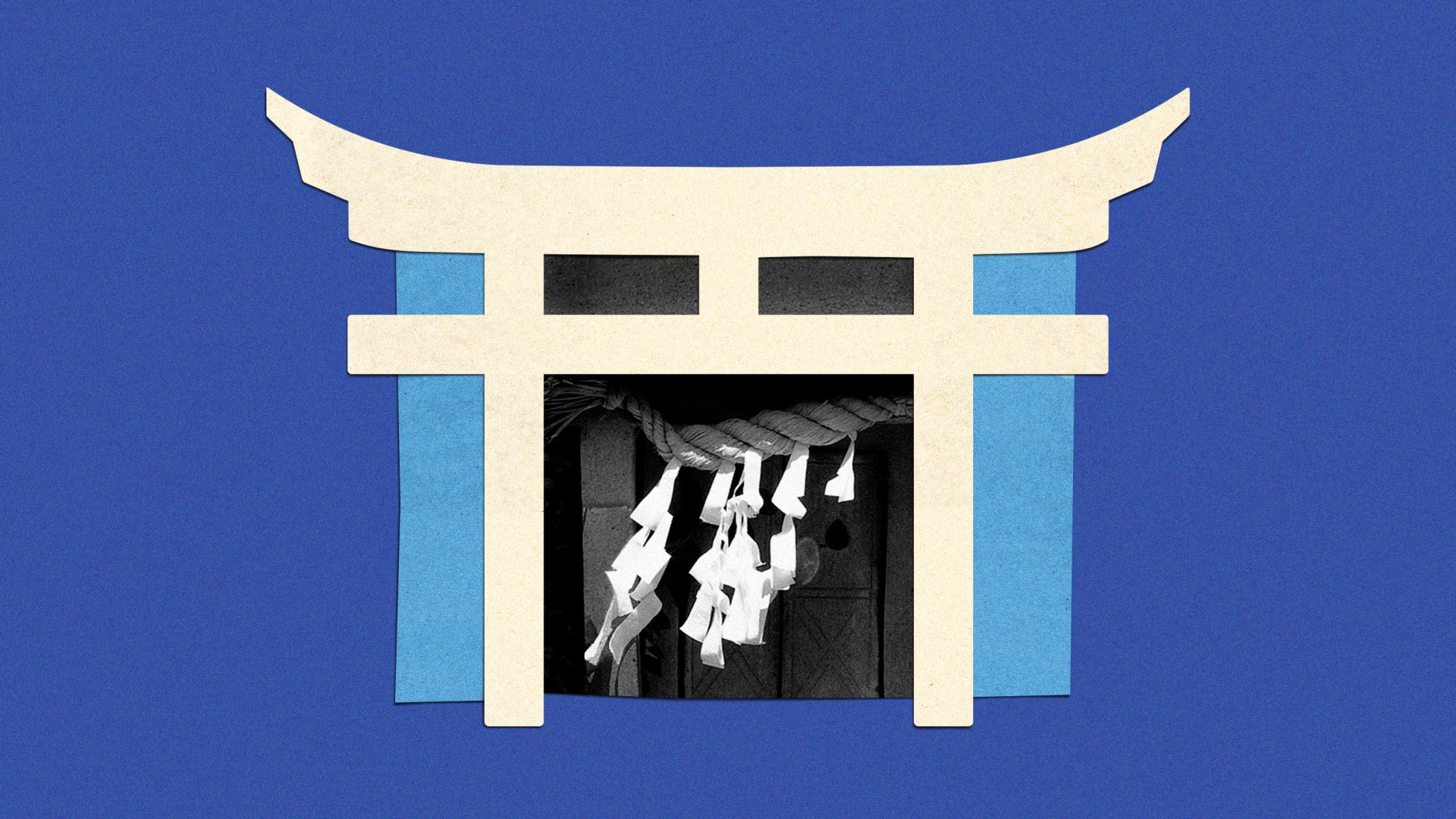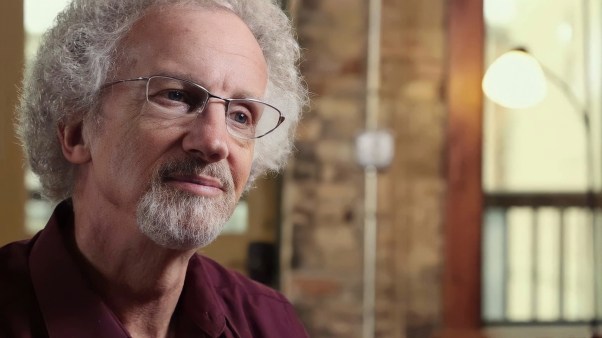クリスチャニティトゥデイは、神道や日本のナショナリズムをキリスト教信仰と融合させようとしたクリスチャンの動きの始まりと、現代日本の福音派が神道的風習に関して直面する闘いについて、東京基督教大学国際宣教センターの山口陽一センター長にインタビューした。
日本のクリスチャンや教会は、過去に神道とどう関わってきましたか?
19世紀半ばにプロテスタント宣教師が初めて来日した時、神社は偶像であると教えました。初期の日本人クリスチャンはこの見解を受け入れ、地元の神社参拝といった神道の慣習に参加するのを拒みました。
しかし、神道信仰とのこうした度重なる対立を通じて、日本人クリスチャンは考え直すに至ります。先祖崇拝や天皇崇拝などの神道の伝統的価値観は、本当にキリスト教信仰と相容れないのだろうかと。
日本的キリスト教運動は、明治初期に始まり、第二次世界大戦終戦まで続きましたが、神道およびナショナリズムをキリスト教信仰と融合させようとしました。この運動の主唱者は、神は欧米の侵略に対するアジアの保護者として日本を選んだのだと考えました。中には、神道の価値観はキリスト教を通して完全に実現される、あるいは日本の天照大神はイエスであり、したがって天皇はキリストの子孫だとまで主張する人もいました。
日本の初代プロテスタント共同体は、横浜バンド(「バンド」はクリスチャンの小集団の意味)とその横浜公会など、国学に精通した人々で構成されていました。彼らのキリスト教理解は、神道を含む日本的精神を重んじる伝統からの回心ではなく、むしろその再解釈でした。
日本人クリスチャンによる神道再解釈の例を挙げていただけますか。
19世紀後半以降、日本人クリスチャンリーダーの植村正久や内村鑑三らは、キリスト教を武士道に接ぎ木されたものと考えることを提案しました。彼らは、名誉や忠誠といった武士道の核となる美徳が、日本のキリスト教のためのお膳立てをしたと主張しました。
その他に、海老名弾正や渡瀬常吉などのクリスチャンリーダーは、神道とキリスト教の融合を、もっとあからさまに試みました。海老名は男女平等などの近代的価値観を支持していましたが、日本は神に選ばれた国だという神道思想のゆえに、日本の優位性を強く確信してもいました。
私は以前、海老名や渡瀬などのクリスチャン思想家は過激だと思っていましたが、当時の日本的キリスト教運動の文献を読んでみて、彼らの考え方は当時としては例外的ではなかったことに気づきました。彼らの姿勢は、日本を含む東アジアが欧米の植民地化の脅威に直面していたという、その環境下で形成されたのです。
日本は帝国主義列強の犠牲者となってはならないという信念があったゆえに、神道思想および愛国精神をキリスト教信仰と融合させていった、クリスチャンの一世代が生み出されました。
現代の日本の福音派が、神道に関して直面している緊張や葛藤にはどのようなものがありますか?
国家神道と、それが第二次世界大戦中に信教の自由を阻害したという歴史の記憶のせいで、日本人クリスチャンは、天皇崇拝や神社参拝、神道の慣習に関係する自治会への参加となると、警戒心や不安感を抱きます。
しかし、神道との関わりを避けようとする姿勢は、近年、鈍化しています。特に若い世代の福音派の中ではそうです。長いものには巻かれて調和しようという考えが強まっています。神社の氏子制度はすたれてきていますが、「自由に生き、助け合い、迷惑をかけないようにしよう」という調和の精神が、日本社会に依然として強い影響力を発揮しています。
今日、制度としての神道は弱体化してきています。でも、日本人はやはり神道精神を高く評価しています。互いの尊敬、調和、慎みなどです。こうした世界観は、社会の均質化に向けて作用し、そういう社会でキリスト教の排他的な主張を信じるのはむずかしいです。そういう意味で、神道精神は制度がなくても生き続ける可能性があります。
天皇もイメージが刷新されました。今では神的存在というより、日本の良心の模範のように広く理解されています。そんなわけで、若い福音派の間では、天皇に対する感謝の念が強まっています。多くの人は、天皇と、国家神道儀式で天皇が果たす役割に対し、以前より嫌悪感を抱かなくなりました。
このように天皇と神道的世界観を肯定的に受け止めるになるにつれ、日本人クリスチャンは混合主義という落とし穴に再び陥らないよう注意する必要があるでしょう。
本シリーズには、「神道の中核にある教え」、日本社会における「神道の歴史的・今日的影響」、神道の影響下にある社会におけるキリストに関する会話についての記事がある。